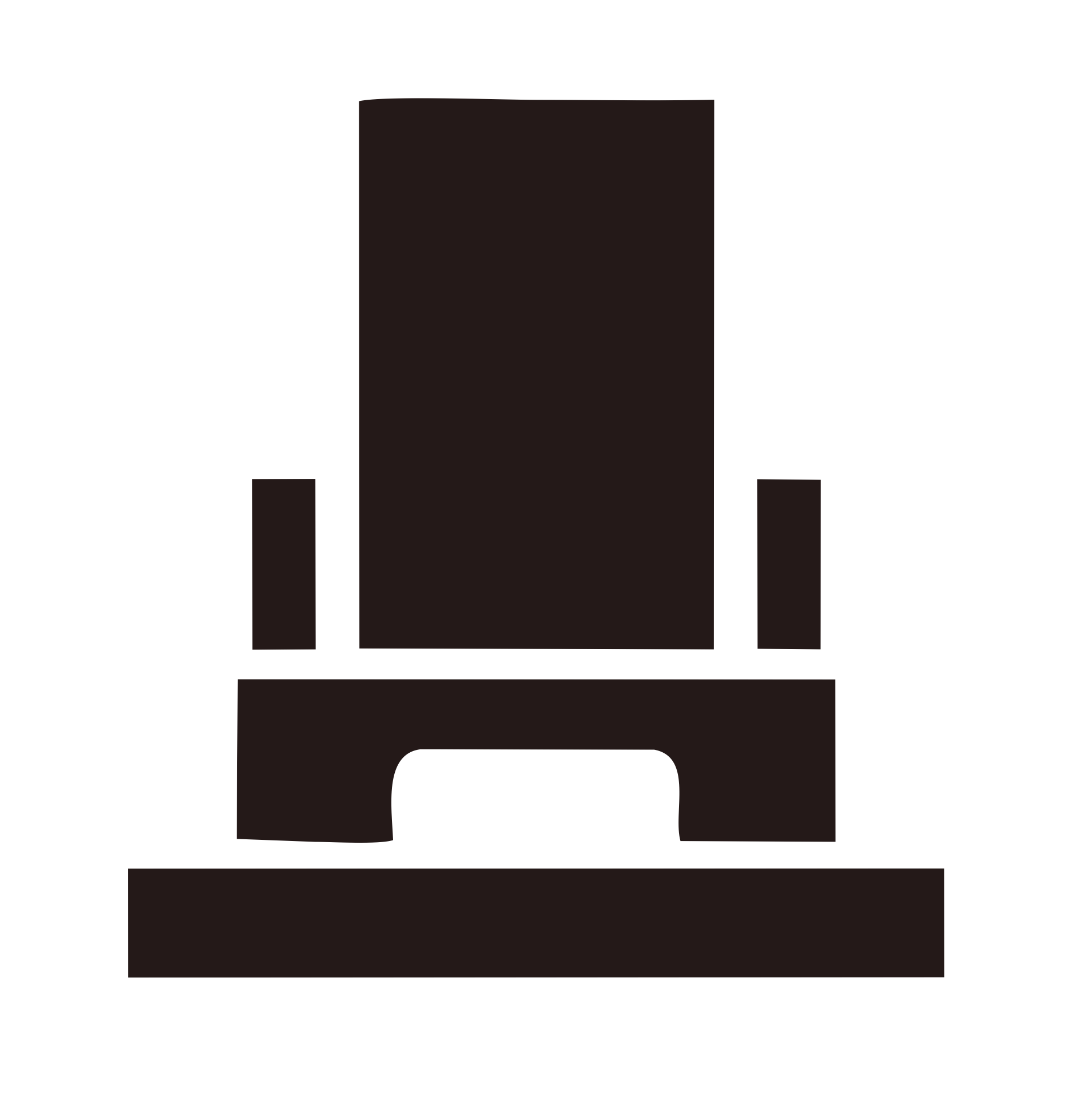トリセツ Q&A
このページでは、お寺の取り扱い説明書=「トリセツ」をイメージした情報と、実際に皆さんから多く寄せられているご質問、お寺からの回答をご紹介します。
「トリセツ」では、いわゆる”お寺とのお付き合い”についてのガイドブックです。
皆さんは”檀家になると大変そう””面倒くさい”というイメージをお持ちではないですか?お寺としては、安心してお参り頂けるようにお伝えしていきます。
【重要】
このページの情報は、現在の西光寺としての在り方を載せています。
仏事は、宗派・地域・個別の寺院によって、多種多様です。ですから、この情報を以て、他の宗派・他寺院に直接当てはめたり、「他の寺はこうだった」との批判・交渉材料にはなさらないように、お願い申し上げます。
お仏壇の処分をお考えの方へ
やり方や流れなど
お仏壇の引っ越し・買い換え・新規購入について
お墓じまいの流れや概算など詳しいご案内

お年忌について
一周忌・三回忌など、故人のご命日から数えて、決まった年するお参り(お年忌)について
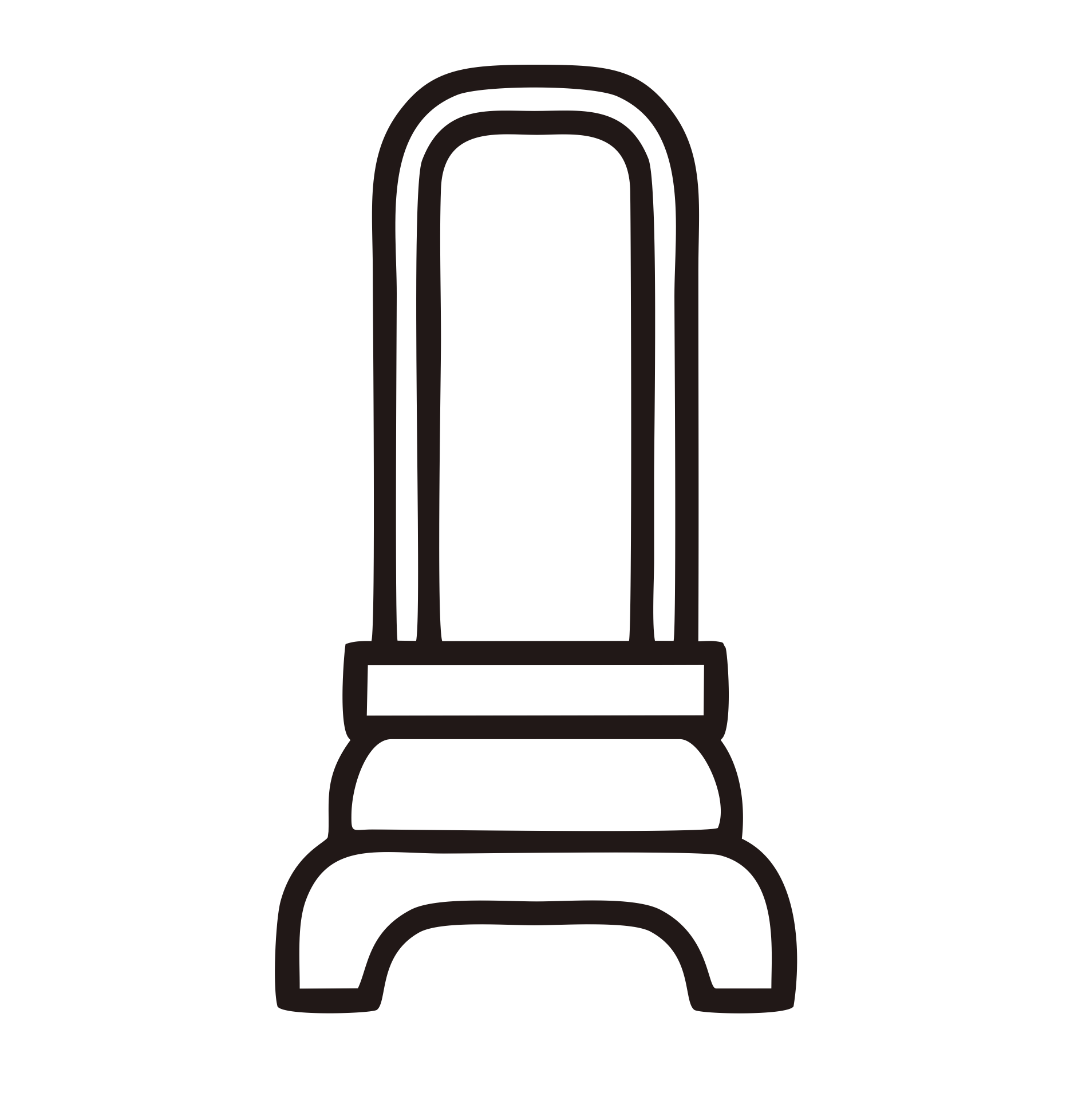
お位牌について
故人の戒名を彫りこみ、自宅で祀る「お位牌」について
<お仏壇じまいについて>
<お仏壇をしまう前に…>
止むにやまれず、お仏壇を処分しなければと悩んでおられると思います。
全てを処分してしまう前に、お伝えしたいことがございます。
本尊様(ほんぞんさま:小さな仏像、もしくは仏様の描かれた掛け軸)や、お位牌(おいはい:戒名の彫られた板)、は小さな場所でも祀ることがでるということです。
具体的には20cm 四方のスペースがあれば、祀ることができます。
例えば、「施設に引っ越さなければならないから、全部処分しなくちゃ」とか「小さなアパートに引っ越すから全部処分したい」と思い込んでいた方も、全てを処分せず、本尊様とお位牌だけを祀ることもできますから、ご一考いただければ幸いです。
<お仏壇を処分したい>
お仏壇そのものに関しては、基本的に2種類の処分方法があります
①仏具店に連絡をして、有償で引き取ってもらう方法
・・・仏具店さんにご連絡いただき、引き取っていただきます。料金は各仏具店さんにお尋ね下さい。
②各自治体のルールに従い処分する方法
・・・豊橋市のルールでは仏壇は「大きなごみ」のカテゴリーに入ります。
この場合、「戸別収集をしてもらう」か、「資源化センターに予約をして、ご自身で持ち込むか」の2パターンになります。詳しくは市のHPをご覧下さい。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/6212.htm#oogomi
<中に入っているものを確認しましょう>
一口に「仏壇を処分する」と言っても、お仏壇には色々なものが祀られています。それぞれ、処分できるものとやり方について、4種類に分けて大まかにご説明します。
①本尊
“ほんぞん”と読み、通常は真ん中の一番上のところに祀られているものです。
曹洞宗では釈迦牟尼仏、つまり、お釈迦さまを本尊としています。一般的には20cm 未満の仏像が多いです。もしくは小さな掛け軸に仏様の絵が書いてあるものもあります。どちらも本尊様として大事に祀ります。
②位牌
亡き方・ご先祖様のお名前(お戒名)が彫られた木の板です。
③仏具
一般的には、ローソク立てや線香立て、お花立て(これらを三具足、と言います)や、おりん(拳ぐらいの大きさの鐘・チーンとならす)・木魚(お経を読むときに叩くもの)などを指します。また広義には「ご遺影」も含まれます。
④仏壇
本尊様つまり仏様を祀る木製の祭壇です。
<種類別での処分方法>
①②はお寺で引き取ります。この時にお精抜き(おしょうぬき:俗に言う魂抜きのこと)をし、お寺でお焚き上げをします。(御布施不要)
③は自治体のルールに従ってご自身で処分できます(仏壇と一緒に仏具店さんに引き取っていただくことも可能です)
*ご遺影もご自身で処分できますが、どうしても気になる方は、お寺へお持ち下さい(無料)
④は基本的には仏具店に連絡して引き取ってもらいます
西光寺は仏壇そのものに関しては、お精抜きをしません。
<お墓じまいをご希望の方へ>
<お墓じまいの流れ>
*墓地の場所と、お骨の行先によって、手続きが異なります。まず最初にQ1,2をご確認ください。手順は1~5となります。
Q1:現在お墓は・・・
A:西光寺にある →Q2へ
B:西光寺以外の場所にある
①お墓の管理者に撤去する旨をご連絡ください。
例1)市営墓地(向山・飯村など)→市役所
例2)集落墓(柱・幸など)→各担当者や町内
②「改葬許可申請書」を入手・提出してください。改葬許可申請書は、墓地のある自治体に提出します ●豊橋市=福祉政策課(市役所東館3階、0532‑51‑2355) ↓Q2へ
Q2:墓じまいしたら、お骨は・・・
A:お寺の合同墓に納めたい
→合同墓申込書をご記入ください(申込書はお寺にあります。墓じまい当日でも記入いただけます。合同墓納骨のお布施は、一家で10万円程度です)
B:他の霊園に持っていく
→行先の霊園の指示に従ってください。上記②の改葬許可申請書は必須になります
1.墓石店にご自身で電話してください
<お伝えいただくこと>
・お墓の場所と、下見の日程 (見積もりの要不要)
・墓じまいの希望時期(いつ頃に撤去できるか、墓石店の都合も聞く)
・ご自身の連絡先
墓石店は、基本的にご自由にお選びいただけます。ご不安な方は、
●Kサポート(西光寺のお檀家さん)090-8488-4989
●若山石材(つつじヶ丘) 61-7220
●かけひ石材(池見町) 61-7555 のいずれかが安心です。
2.西光寺(0532-52-4203)に電話してください
<ご相談ください>
・お墓じまいのご希望日、もしくはご希望の時期(*必ず墓石店の撤去日以前にご設定ください。時間帯は基本的に何時でも承ります)
・お墓じまいの所要時間は15分から25分程度です(お墓の状況により前後します)
・お骨の行先(合同墓/他の霊園)
*お精抜きの時に、墓石店の立ち会いを希望される場合は、その旨、墓石店に事前にお伝えください。
3.当日までにご準備いただくこと・もの
・「改葬許可証」の取得=改葬許可申請書を提出・受理されると発行されます(*西光寺以外の墓地の方、もしくはお骨の行先が西光寺以外の方のみ必要です)
・お墓の掃除(*長年お参りした大切な墓地です。最後の報恩行として、きれいにしましょう)
・家族、親族へお墓じまいの日程連絡(大切なお参りですから、ご家族、ご親族もお声がけいただければ宜しいかと存じます)
・服装は華美でないものなら平服で結構です(礼服は不要です)
・当日の持ち物・・・
◆お花(お墓用)
◆お線香
◆軍手
◆汚れて良いタオル(1~2本)
◆お布施(お精抜き=3万円程度)
(お骨を車で運ぶ場合は、上記のものに加えて・・・お骨を入れるダンボール + ビニール袋(スーパーの袋で結構です)
4.当日は、お墓の前にご集合ください
・お花を供えます
・お精抜きのお参りをします。(お線香を立てて、お参りいただきます。)
・続いて、皆さんでお骨を取り出していただきます。(軍手とタオルをご用意ください)
・所要時間は15分から25分程度です。(お骨の状況により前後します)
・お骨が取り出しにくい場合は、一部のみを納骨します。後日、石材店さんが墓石を撤去した後に、お寺で再度納骨供養をします。
↓お骨をもって移動(お骨の行先 A/B によって異なります)
A:合同墓に納める方(所要時間は5~10分程度)
・お骨を納め、納骨のお経を読みます。お線香をあげてもらいます。
・終了後に、寺務所にてお布施をお納めください
(お精抜きは3万円程度・合同墓納骨は10万円程度)
・合同墓申込書をご提出/ご記入ください
B:その他の霊園へ納める方
・終了後に、お布施をお納めください(お精抜きは3万円程度)
・お骨をお持ちいただき、お気をつけてお帰りください
5.墓石店に電話をしてください
・お精抜きをしたことをお伝えください
・西光寺以外のお墓の方は、各霊園のやり方に従い、手続きをしてください(特に市営墓地は、撤去後に市役所への届け出が必要です)
・墓石店より請求書が届きますので、お振込ください
<お仏壇について>
~ お仏壇を引っ越したい・小さくしたい・初めて設置される方へ ~
「今まで祀っていたご両親の大きな家から、自分たちの住むマンションに持ってくるので、あんなに大きな仏壇は入らない」とよく耳にします。
現在はスリムな仏壇や、かなり小さなサイズまでデザインも様々あります。皆さんの気に入ったものをお求めください 詳しいご案内はこちら
<お仏壇を買い換えたい>
通常は新しく購入をした時に、古い仏壇はお店が引き取ってくれることが多いようです。(料金は各仏具店にお問い合わせください)西光寺では、仏壇単体にはお精抜き(魂抜き)をいたしません。
<お仏壇を新しく設置する>
新しく仏壇を購入され、ご自宅に安置をされた後、こちらからお参りに伺います。
これを安座諷経(あんざふぎん)と申します。このお参りは「ここに仏壇(本尊様)をお迎えし、ご安置しますので、これからよろしくお願いいたします」という意味を込めた、いわば「ご挨拶のお参り」です。お参り後には、簡単にお参りのやり方、仏具の種類についてご説明します。
こちらからご自宅へお邪魔しますので、ご都合の良いお日にちをお聞かせください。(時間は30分程度・お布施は1~2万円の方が多いようです)
仏壇に祀る・設置するものは、大きく分けて以下の3つになります。お仏壇と同時に購入される方がほとんどです。(仏具店さんに行く前に、ご一読いただくと結構です)
お仏壇と同時に本尊さまやお位牌をご購入されましたら、同時にお精入れ(おしょういれ:魂入れ)をいたします。
①本尊
“ほんぞん”と読み、通常は真ん中の一番上のところに祀られているものです。曹洞宗では釈迦牟尼仏、つまり、お釈迦さまを本尊としています。一般的には20cm 未満の仏像が多いです。もしくは小さな掛け軸に仏様の絵が書いてあるものもあります。どちらも本尊様として大事に祀ります。
②位牌
亡き方・ご先祖様のお名前(お戒名)が彫られた木の板です。
③仏具
一般的には、ローソク立てや線香立て、お花立て(これらを三具足、と言います)や、おりん(拳ぐらいの大きさの鐘・チーンとならす)・木魚(お経を読むときに叩くもの)などを指します。
<お仏壇を引っ越したい>
引っ越し前にお参りはいたしません。(お精抜き不要)本尊様やお位牌は、タオルなどで丁寧に包んでお引っ越し下さい。
<引っ越しをした後は・・・>
安座諷経(あんざふぎん)をいたします。このお参りは「ここに仏壇(本尊様)をお迎えし、ご安置しますので、これからよろしくお願いいたします」という意味を込めた、いわば「ご挨拶のお参り」です。
こちらからご自宅へお邪魔しますので、ご都合の良いお日にちをお聞かせください。(時間は20分程度・お布施は1~2万円の方が多いようです)
<位牌を小さくしたい>
「仏壇を買い換えるとき、今までの位牌が大きくて入らないので、小さくしたい。」という方も多くいらっしゃいます。また、それとは別に「古くなったので新調したい。」という方もいます。
この場合は、安座諷経(あんざふぎん)の時に、古い位牌のお精抜きをし、新しいお位牌にお精入れをします。(古い位牌はお寺で引き取ります)
<本尊様や位牌を修理・塗り直したい>
こちらの場合は、修理・塗り直しの前にお寺にお持ちください。お寺でお精抜きをするので、それが終わったら仏具店にお持ちください。修理後にもう一度、お精入れをしますので、お寺にお持ち下さい。(お布施は、お精抜き・お精入れを合わせて1~2万円の方が多いようです)
<本尊様や位牌を新調したい>
お精入れをしますので、お寺にお持ち下さい。ご自宅にお邪魔してお精入れをすることもできますので、お気軽におたずねください。(位牌は四十九日に精入れします)